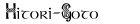>>> ヒトリゴト:不登校
2016.06.29 updated.
うちの子供たちは、現在不登校中。上の子はもう1年近く学校に行っていない。
不登校の子は決してダメな子なんかじゃなく、不登校の子の親が決して皆ダメ親なんかじゃなく、ただ、自分を強く持っている子だったり、感性が豊かな子だったりするだけなんだ。だから、その個性を削ったり、押し込めたりせず、その子を信じて、恐れずその子なりの人生を歩ませてあげよう。その生き方を社会でも認めてあげて欲しい。そんな想いでこのヒトリゴトを書いている。
学校に行くのが当然の世の中にあって、上の子が学校に行かなくなるまでの過程は、今考えると相当痛々しい。
始め、上の子が学校に行くのが辛くなった時、私は「中学校まではちゃんと通っておいた方がいい。逃げてもだめ」等と言ってなんとか通わせようと頑張った。理由を探り、それを解決すれば通えると思っていた。しかし、そんな単純なことでは無かった。無理に行かせた結果、子供は顔は蒼白、夜は眠れず、学校に行けば冷や汗をかき、吐く、アトピーは悪化し血だらけ汁だらけになった。ここまできてやっと、「学校、休んでいいよ」といってあげることができた。なんでここまでボロボロになるまで頑張らせてしまったのだろうかと、今ではとても後悔している。
ちなみに、下の子が学校に行かなくなってしまった時、「まだそこまで行ってないと思う」という意見もあった。しかし、そこまで行くと、再び立ち上がることができるようになるまで、下手すると何年もかかることになる。
学校に通えなくなるのは、9割がた家庭に問題があると言っている人もいる。確かにそうなのかもしれない。
我が家はいたって平和だけれど、愛情不足なのかも、過干渉なのかもと色々悩んだ。しかし、完璧な親なんてどこにもいないと思う。とはいえ、こんなことがあったお陰で、前よりずっと子供たちに向き合うようになった。あなたはあなたのままでOKと思えるようになった。これはある意味よい機会だったと思う。
そして、今思うのは、「とにかく、誰のせいでもない、この子はこの環境には合わなかったのだ」ということ。
明るい家庭、温かい家庭、賢い親の対応があれば、それも耐えていけたのかもしれないが、私は学校は修行の様に耐える場所ではないと思う。考え方は様々あると思うが、私は、子供たちにこの人生、耐えて耐えて生きていくのではなく、生き生きと、喜びいっぱいに生きていって欲しいと思っている。考え方次第、気持ち次第で、どのような環境でも楽しいものに変えることはできるとは思うが、年齢的にもそれが難しかったりする場合は環境を変えることも大事。あと、通えない、耐えられない子を、「ダメな子」「ワガママな子」とレッテルを貼るのは絶対賛成できない。
今、不登校児が非常に増えている。昔に比べ、自分を持った子が増えているのかもしれないし、ちょっと変わった子、ちょっと感受性の強い子は居辛い学校環境なのかもしれないし、理由は私にはよくわからない。でも、いずれにしても、学校も多様性が求められる時代になってきたのではないかと思う。残念ながら、私の住む那須町には公立の小学校、中学校しかない。もっと色んなタイプの学校から自分にあった学び方、環境を選ぶことができたら。。。とつくづく思う。
色々悩み、考えもしたけれど、今は、この子達、人生のレールから脱線したわけではないと思っている。むしろ、自分なりの人生を歩み始めたのだ。せっかくだから、自由に生き生きと羽ばたいて欲しいと思っている。親として、そのサポートをしてあげたいと思う。まだまだ時間はかかりそうだけれど、焦りは禁物。
すべての出来事は必然であり、完璧なタイミングで、完璧に起こっていると昔学んだことがある。先日友人と話してそのことを思い出した。この出来事も、子供にとって、自分にとっても、人生において完璧な流れなのだと思う。だから、この先にはきっと素晴らしい未来が待っている。確かに、子供が学校に行かなくなったことで、沢山のことを学んで、沢山の人たちに助けられ、色んな出会いがあった。
どんなことも、良い、悪いと判断せず、まず受け入れるということもその友人に学んだ。そして、子供たちを丸ごと「大丈夫」と信頼するということも。そう思ったら、とっても気分が楽になった。どんな道を子供が選ぼうと、大丈夫!その信頼があれば、きっと子供たちは自分らしい人生を、生き生きと生きていけると今は思う。
不登校になることで、不安を抱える子、親御さんたち、たくさんいると思うけれど、大丈夫!道はいくらでもある!むしろ、「君たち、なかなかやるな!」「実は、君たちの未来は無限で明るい!」とすら思っていいる^^不登校児は、実は全然かわいそうなんかじゃないんだよ^^
最後に、悩んでる私の話を沢山聞いてくれ、助けてくれる友人たち、子供のために親身になってくださっている先生方に感謝!これからも、私たち親子を応援してくださいね!










(小島美紀)